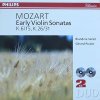
ヴェルレ Blandine Verlet (hc), プーレ Gerard Poulet (vn)
1974-75
| 17 age |
61 5 |
62 6 |
63 7 |
64 8 ▲ |
65 9 |
66 10 |
67 11 |
68 12 |
69 13 |
70 14 |
71 15 |
72 16 |
73 17 |
74 18 |
75 19 |
76 20 |
77 21 |
78 22 |
79 23 |
80 24 |
81 25 |
82 26 |
83 27 |
84 28 |
85 29 |
86 30 |
87 31 |
88 32 |
89 33 |
90 34 |
91 35 |
92 |
ソナタ ト長調 K.9
〔作曲〕 1764年1月 パリ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1764年4月にド・テッセ伯爵夫人(Adrienne-Catherine Comtesse de Tesse, 1741-1814)に「作品2」として贈った2曲(K.8 と K.9)のソナタの第2。 ピアノとヴァイオリンのためのソナタとしては第4番にあたる。 夫人はヴォルフガングに小さな時計をくれたという。 モーツァルト一家がパリ滞在中、世話になっていたグリム(Johann Friedrich Melchior von Grimm, 1723-1807)が献辞の文を書いたが、最初それを伯爵夫人が受け付けなかったので、献辞を書き直したという。 そのせいで、この曲の版刻(印刷)が遅れたという逸話が残っている。 また、レオポルトは息子の間違い(最後のトリオでヴァイオリンの連続3つの五度)を訂正したかったが、直されないまま版刻されたという。
私にとって残念なのは、校正をしたあとでも、いくつかのあやまりが版刻や改訂にも残ってしまっていることです。 版刻をしてくれた女性と私の二人は、たいへん場所が離れていましたし、万事急いでしたものですから、再校の試し刷りをやらせる暇がありませんでした。 このことが原因で、殊に作品2のいちばん最期のトリオでヴァイオリンの連続3つの五度が残ってしまいましたが、これはわが幼き作曲家氏が犯したもので、あとで私が訂正しましたが、お年寄りのヴァンドーム夫人がそのまま残してしまったものです。「作品2」はハ長調ソナタ(K.6)から始まる4曲の通称「パリ・ソナタ」の後半にあたるが、これは当時パリで活躍していたドイツ人作曲家たちの作品をモデルにしている。 しかし年齢的に人生経験の浅い少年作曲家には越えられない壁があり、「その外的な衣裳の点で内的な作風の点でも、なによりもまずショーベルトのモデルを追随しているが、しかしこの模倣は彼の年齢にふさわしいもので、子供らしく誠実である」とアインシュタインは言い、次のように続けている。[書簡全集 I] p.200
20年後のモーツァルトが、緊張、エネルギー、力においてヨーハン・ショーベルトを百倍も凌駕しているように、少年モーツァルトは百倍も劣っているのである。 ショーベルトの芸術は、8歳の少年が理解したり模倣したりしえないような、深みと予想外のものを持っている。 そして、ショーベルトはシュレージェン人で、ポーランドとの国境付近の出身だったので、しばしば民族的な魅力を持つポロネーズを(たいていは中間楽章として)書いたが、幼いモーツァルトはそれに対してカンタービレな、メロディーの点では特性のないメヌエットを対立させることしかできなかった。それでも非凡な少年は独自の世界を切り開こうとしていた。[アインシュタイン] p.166
これら4曲のソナタの最後のもの、ト長調はすでに、ことに第1楽章の展開部においては、ショーベルトの模範から取られた型を打破している。同書
このソナタは4曲中一番規模が大きく、著しく進境を示していると評価が高い。 終楽章の主題はピアノ協奏曲(トルコ行進曲付き)K.331 の第1楽章第2変奏に似ていることも知られている。
〔演奏〕
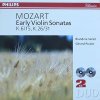 |
CD [PHILIPS PHCP-9081-2] t=14'22 ヴェルレ Blandine Verlet (hc), プーレ Gerard Poulet (vn) 1974-75 |
 |
CD [音楽出版社 AEOLUS OACD-2] t=8'40 小林道夫 (hc), 岡山潔 (vn) 1991年8月、埼玉県松伏町、田園ホール・エローラ |
〔動画〕
〔参考文献〕
| Home | K.1- | K.100- | K.200- | K.300- | K.400- | K.500- | K.600- | App.K | Catalog |